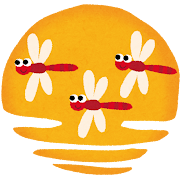ブログ
11月ブログ再開と営業のお知らせ
🍁ブログ再開と営業のお知らせ
今年は紅葉がひときわ美しいですね。
秋が短く、一気に気温が下がったせいか、街の色づきも早いように感じます。
しばらくお休みをいただいておりましたが、ようやく少しずつ、いつものペースを取り戻せそうです。
お休みの間に身の回りの状況が変わり、お店の営業や鑑定のスタイルも、今までと少し変えていくことになりました。
来年に向けては、商品の販売を少しずつ縮小し、鑑定と講座を中心に展開してまいります。
【お店の営業について】
営業日は 火曜日と金曜日の10時〜18時 です。
(13時〜15時は休憩時間となります)
それ以外の日は、鑑定の予定が入っていない時間は同じ時間帯で営業しますが、
基本的には鑑定業務を優先させていただきます。
【鑑定について】
できる限りこれまでと変わらず対応いたします。
ただし、今月より 毎週木曜日の新橋での鑑定は終了 となりました。
代わりに、第3・第4金曜日は錦糸町マルイ3階「アリーナ」 にて鑑定を行います。
都内での個人鑑定は引き続き承っております。
ご希望の方は、メールまたはお電話でお気軽にご相談ください。
詳しくはホームページの「占いのご案内」ページをご覧ください。
【貸し教室について】
お休みしていた貸し教室も、枠を拡大して再開しました。
用途に合わせて、さまざまな形でご利用いただければ幸いです。
【SNSの再開について】
SNSの更新もしばらくお休みしていましたが、
現在は 毎朝の音声配信「毎朝3分 開運ごはん」 から少しずつ再開しています。
今月からは、これまでの「開運ごはん」のメニューに加えて、
花言葉や香り、色など“ごはん以外の開運ヒント” もお届けしています。
心と暮らしのリズムを整える小さなきっかけとして、ぜひ毎朝の配信をお楽しみください。
今後は Instagram、そして このお店のブログ と順に発信を再開していく予定です。
新しい形で、季節の話題や日々の開運メッセージをお届けしてまいります。
年内は少しずつペースを整えながら、できることから丁寧に進めていきたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
新しい風とともに~次のステージへ
先日のブログでも少し触れましたが、
9月以降、身のまわりの変化が続いており、
インスタや音声配信も、しばらくお休みをいただいております。
ようやく一山越えたところですが、
今度は体調の波もあり、もう少しだけ静養期間を続けることにしました。
来週あたりから、少しずつ元のペースを取り戻せたらと思っています。
温かく見守ってくださっている皆さま、本当にありがとうございます。
さて、グランジェの柱である鑑定についてお知らせです。
浦和のお店を中心に活動していくことに変わりはありませんが、
しばらくの間は新橋・原宿での出演をお休みいたします。
その一方で――
来月から新しい鑑定場所が加わる予定です。
まだ詳細はお伝えできませんが、
都内で定期的に鑑定できる場として、ただいま準備を進めています。
都内での鑑定をご希望の方は、
メール・お電話・InstagramのDMなどからお気軽にご連絡ください。
個別にスケジュールをご案内いたします。
人生の節目を感じる出来事が続くこの頃ですが、
たくさんのご縁に支えられながら、なんとか元気にやっております。
お店の営業についても、11月に入りましたら改めてお知らせしますね。
風向きが少し変わったような今、
また新しい季節を迎える準備をしています。
次にお会いできる日を、心から楽しみにしています。
お彼岸の中日&おはぎ
今日は秋分の日、そしてお彼岸です。
ご先祖さまに感謝をお伝えすると同時に、自分自身の心を整える節目でもあります。
お彼岸といえば「おはぎ」。
実はこのおはぎ、五行に分けるとそれぞれ違った運気を宿しています。
🌰あんこ=土金水 → 安定運
🌾きなこ=土金 → 安定運+軽快さ
⚫ごま=火土金水 → 冷静さ・判断力・決断力
🌿ずんだ=木土金 → 新しいスタート運
ご先祖さまにお供えしてから、自分でもひと口いただくことで、自然と運気をいただけるんですね。
今日は少し手を止めて、秋の空を眺めながら、心と運気を整える時間を過ごしてみませんか。
食べながら、季節の流れに寄り添いながら、また明日からの力をいただけますように🍂✨
フォローしてチェックしてみてね!
白露に入りました
夏休みに続き一週間、お店のブログはお休みしてしまいました。
少しのんびりしている間に、季節は着実に歩みを進めています。
二十四節気は「白露」に入り、七十二候もふたつ進んで、今は「草の露白し」の頃。
朝晩の草の上に光る露に、秋の気配を感じますね。
そして、9月といえば「月」。
今夜は満月。先日の夜の配信でもお話ししましたが、中秋の名月は今年は10月にやってきます。
そのあたりのお話にご興味があれば、ぜひ配信をチェックしてみてください。
まだ夏の名残の暑さが体にこたえますが、それでも季節は確実に進んでいます。
涼しい風、虫の声、早まった日の入り…。
小さな変化を一つひとつ見つけることで、毎日の暮らしにささやかな彩りが加わります。
※音声配信と併せてインスタグラムでもフォロワー大歓迎中です
薬膳と四季
先週の土曜日は、暦の節目でした。
二十四節気では「処暑」、七十二候では「わたのはなしべひらく」に入ります。
日本の四季は、風景や文化だけでなく、農業や漁業、そして日々の暮らしの知恵までも暦をベースに成り立ってきました。
中医学を原点とする「薬膳」もまた、四季の移り変わりと体の整え方を重ね合わせた考え方です。
季節ごとの食材をいただき、その季節に出やすい不調をケアする。
まさに暦と深くつながった食事法と言えるでしょう。
今「薬膳」はちょっとしたブーム。書店に行けば、季節ごとの養生法やレシピを紹介した本が並んでいます。
ところが近年の気候は、ただ「暦と少しずれている」というレベルを超えてしまいました。
春夏秋冬のリズムが乱れ、時には季節そのものが飛んでしまったように感じることさえあります。
薬膳の基本は「四季に合わせた食事」です。けれども季節が乱れれば、その前提が揺らいでしまいます。
実際、野菜や果物も、海の魚も、かつての「旬」に合わせて収穫できなくなりつつあるのが現実です。
たとえば梅雨。少し肌寒く湿気の多い時季――そんな印象を、若い世代はもはや持っていないかもしれません
。「梅雨? ゴールデンウィークが終わったら夏じゃない?」という声を聞いたことがあります。
強烈な日差しやゲリラ豪雨、それが今の梅雨のイメージになってしまっているのです。
季節の乱れはまだまだ続くかもしれません。
だからこそ、従来の「四季をベースにした薬膳」に加えて、今の気候に合わせた新しい薬膳の形も考えていく必要があるのかなと。
何となく思ってしまいました。